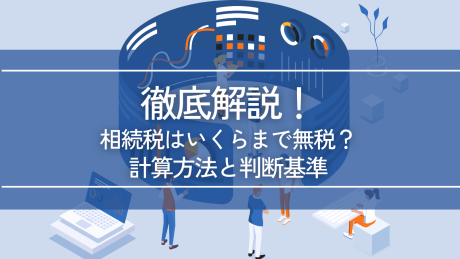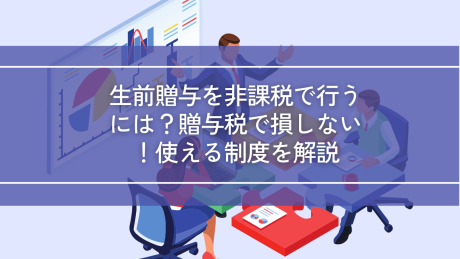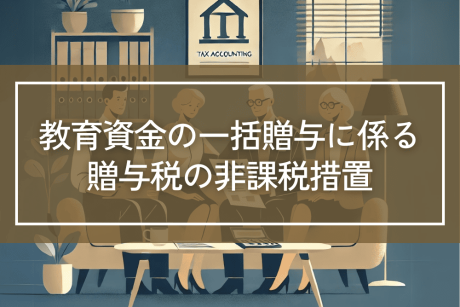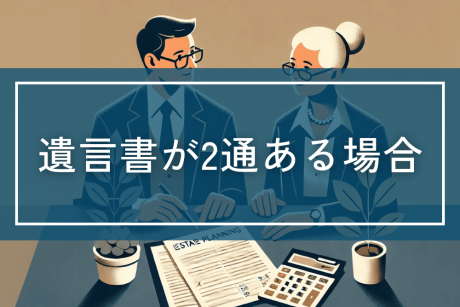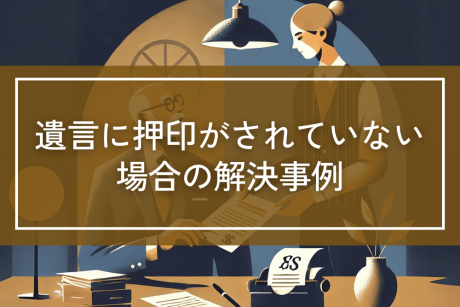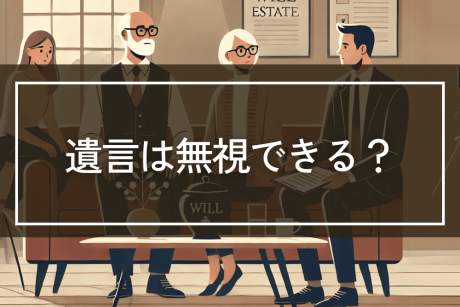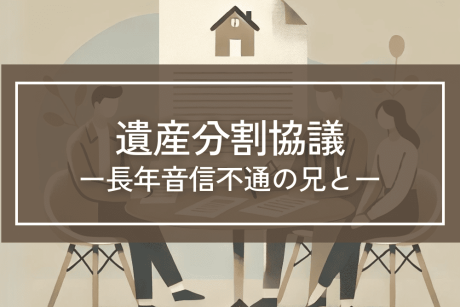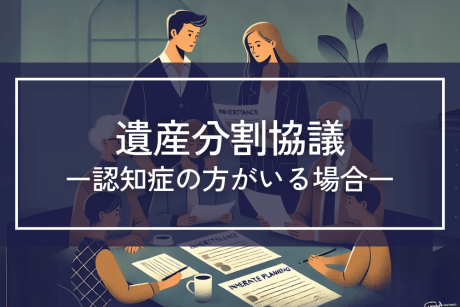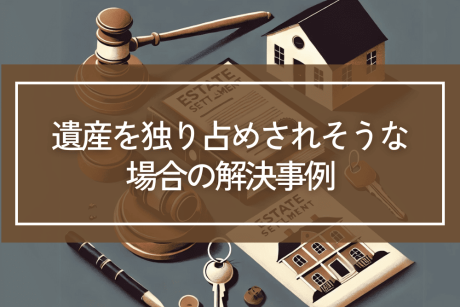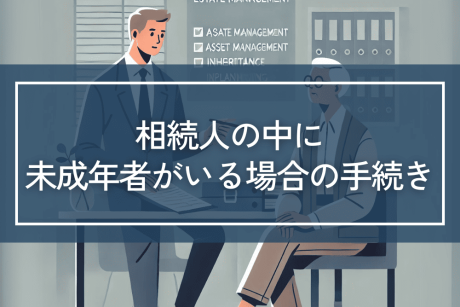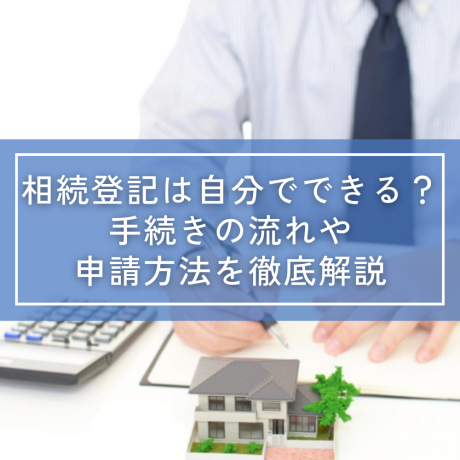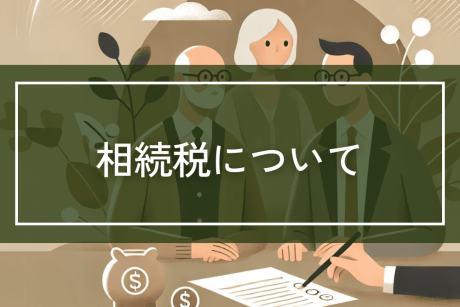
ステップ1:相続対策が必要な方にまず知ってほしい「相続税」の基本
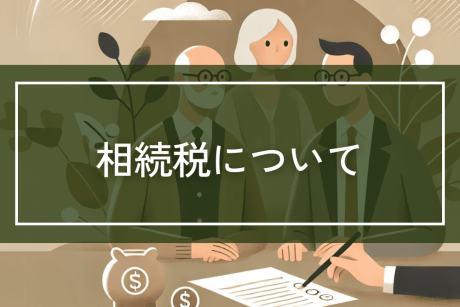
ステップ2:あなたの相続税、いくらかかる? 試算の考え方を解説!
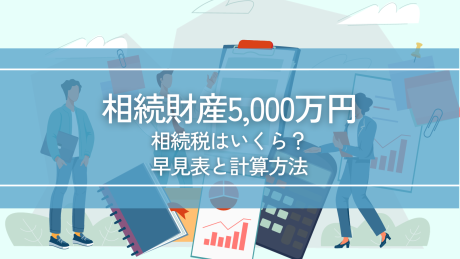
2025.12.24
「相続税」はどうやって決まるの?早見表から計算方法まで解説!
相続税の計算は複雑なうえに、「実際にどれくらいかかるのか?」も分かりづらいですよね。 相続税は配偶者や子どもの人数によっても変動しますから、「早見表」を使ってご自身のあてはまるケースにあわせて調査するのが最も簡単です。 相続税に関する早見表は以下の通り。 ■「配偶者あり」の場合 相続財産 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 5,000万円 40万円 10万円 – 6,000万円 90万円 60万円 30万円 7,000万円 160万
ステップ3-上級編:もっと詳しく知りたい方へ。相続税の仕組みと注意点を深掘り
ステップ4:誰に財産を相続する? 相続人の範囲と基本ルールを整理しましょう
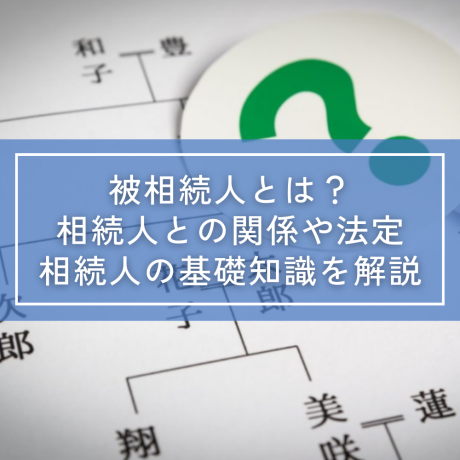
2025.12.17
被相続人とは?相続人との関係や法定相続人の基礎知識を解説
被相続人とは「亡くなった人」のことです。一方で「遺産を相続する人」を相続人といいます。相続を扱うときに使う「妻」や「子」「孫」は、被相続人の立場から見たものです。 相続は被相続人が亡くなると同時に始まり、相続人は死亡時点での被相続人の預貯金・土地・建物・権利・借金などを相続します。 例えば、夫・妻・子がいるケースで、夫が亡くなると被相続人は夫で、妻・子は相続人です。すでに子が死亡しており、孫がいる場合の相続人は妻と孫になります(後述する「代襲相続」と呼ばれるケースです)。
ステップ4-上級編:「誰に・いくら渡す?」を考えるときに知っておくべきポイント
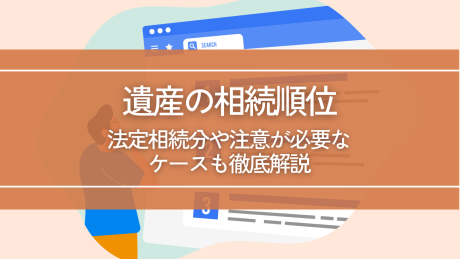
2025.09.19
遺産の相続順位とは?法定相続分や注意が必要なケースも徹底解説
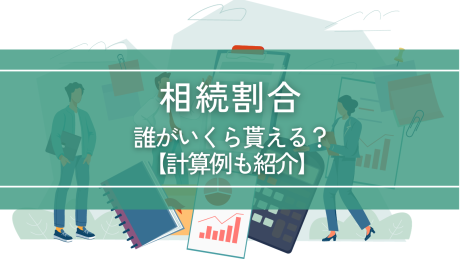
2025.12.24
相続割合を分かりやすく解説|誰がいくらもらえる?【計算例も紹介】
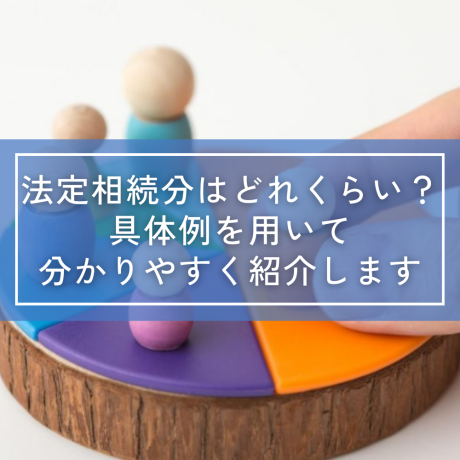
2025.09.22
法定相続分はどれくらい?具体例を用いて分かりやすく紹介します
ステップ5:相続対策は“なるべく早く”が大切です!
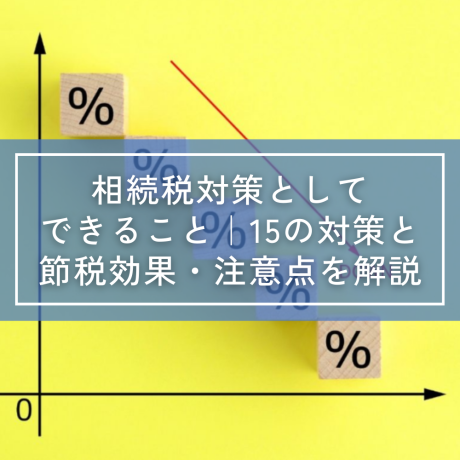
2025.12.24
相続税対策としてできること|15の対策と節税効果・注意点を解説
相続税の節税対策のひとつに「生命保険の活用」があります。生命保険に加入することで、非課税枠の有効活用や所得税の対象となる受け取り方が可能です。特定の相続人や相続人以外の人を受取人に選択できるため、よりご自身の状況に合った相続ができます。
まずは無料初回面談へ
「自分に必要かな?」と迷うことがあれば、
早めに疑問を解消しておきましょう。
ステップ1:相続対策、何から始めればいい? おすすめの準備は?
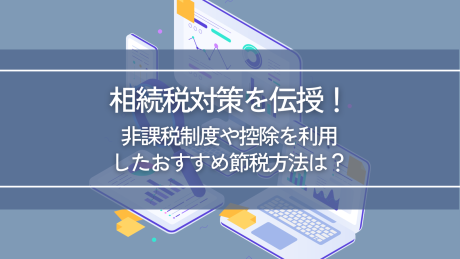
2025.09.12
相続税対策を伝授!非課税制度や控除を利用したおすすめ節税方法は?
相続税は、遺産の総額が多い場合に発生する税金です。遺産が多ければ、その分支払う税金の金額も増えます。ただし、相続税には基礎控除という制度があり、その金額以下になれば相続税はかかりません。 基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出します。基礎控除額を上回る資産については税金がかかりますが、その他の控除や特例、生前贈与の制度などを利用できれば相続税の減額は可能です。
ステップ2:贈与を活用して、財産を少しずつ引き継ぐ準備を始めましょう(生前贈与編)

2025.12.18
生前贈与とは?相続との違いやメリット・注意点を解説
生前贈与をする際には贈与税が発生します。しかし非課税枠があるため、その範囲内で贈れば贈与税はかかりません。 非課税枠の種類は豊富にあります。要件を確認し、どの方法を利用できるかを把握することが大切です。「誰に」「いつ」「何を」いくら」贈りたいかを明確にし、ご自身が納得できる方法を見定めましょう。
ステップ2上級編:“贈与”のコツとは? 制度を上手に活用するためのポイント
ステップ2番外編:まとまった金額を生前贈与したい!そんな時は
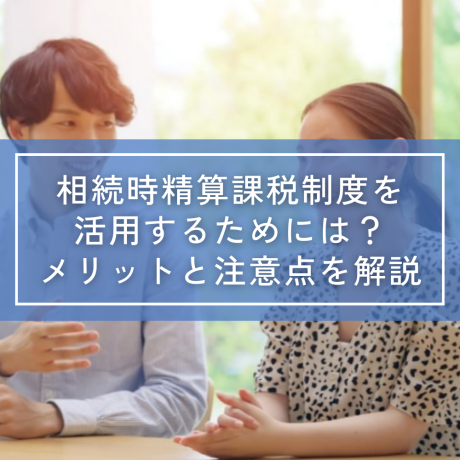
2025.12.16
相続時精算課税制度を活用するためには?メリットと注意点を徹底解説
ステップ3:土地や住宅がある方へ。相続に備えた対策の考え方(不動産編)
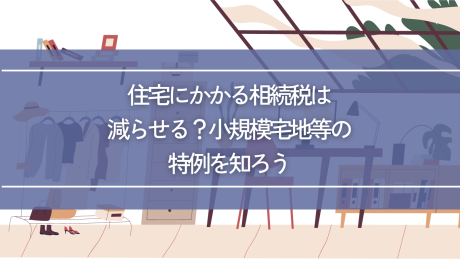
2025.12.16
住宅にかかる相続税は減らせる?小規模宅地等の特例を知ろう
住宅の相続税額を調べるには評価額を知る必要があります。住宅は「建物と土地」に分け、それぞれ別の評価方法で求めます。相続において住宅が大きな割合を占めるケースは少なくありません。したがって、住宅を取得する相続人は多くの相続税を納めることになります。住宅を正確に評価し、正しい納税額を申告しましょう。
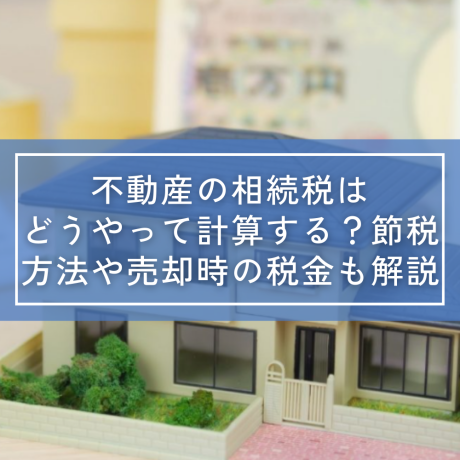
不動産の相続税はどうやって計算する?節税方法や売却時の税金も解説
不動産の相続税評価額の計算方法を土地と建物に分けて解説します。相続税評価額とは、相続税を計算するときの基準となる課税価格です。土地の相続税評価額は、主に市街地のような路線価が定められている土地は「路線価方式」、路線価が設定されていない土地は「倍率方式」を用いて計算します。
ステップ3上級編:活用事例から学ぶ、不動産に関する相続対策の具体例と注意点
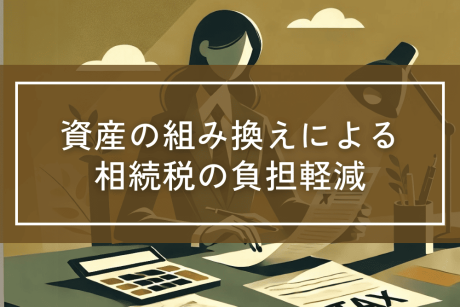
2025.05.14
資産の組み換えによって相続税の節税をする

2025.09.10
広大な庭があるような自宅の土地を一部売却することで相続税を減らす
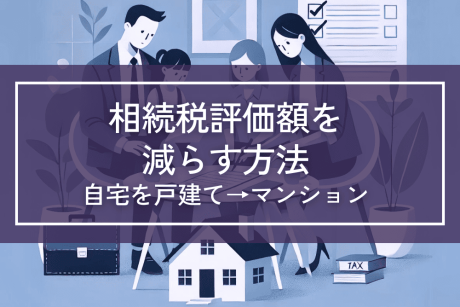
2025.05.14
自宅を戸建てからマンションに買い替えて相続税評価額を減らす

2025.05.14
相続する前に持ち家を売却することで小規模宅地等の特例を適用
ステップ4:あとで困らないために。相続税の支払いに備えた準備を
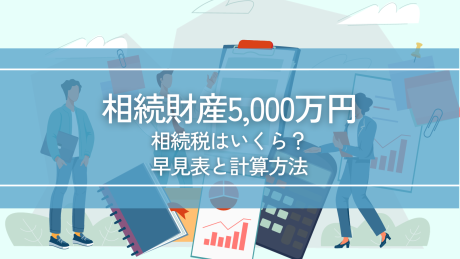
2025.12.24
「相続税」はどうやって決まるの?早見表から計算方法まで解説!
相続税の計算は複雑なうえに、「実際にどれくらいかかるのか?」も分かりづらいですよね。 相続税は配偶者や子どもの人数によっても変動しますから、「早見表」を使ってご自身のあてはまるケースにあわせて調査するのが最も簡単です。 相続税に関する早見表は以下の通り。 ■「配偶者あり」の場合 相続財産 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 5,000万円 40万円 10万円 – 6,000万円 90万円 60万円 30万円 7,000万円 160万
ステップ4-上級編:納税資金を準備するために知っておきたい具体的な方法とは?

2025.05.14
生前贈与として生命保険を活用した納税資金の確保
最終ステップ-相続争いを避けるために。「遺言書」を今こそ考えてみましょう
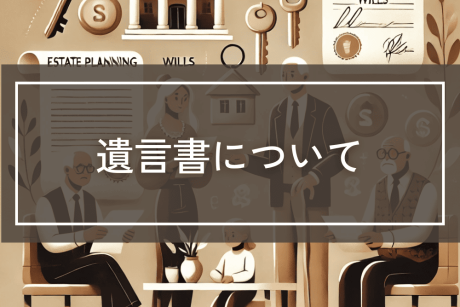
2025.05.14
相続が発生した際に相続争いを発生させないための遺言書
被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。 過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したいときに有効です。
まずは無料初回面談へ
相続対策や事業承継準備の流れや対策を、専門家が寄り添って整理します。
ステップ1 -お役立ち情報:相続手続きの期限は? 相続はしなくてもいい?
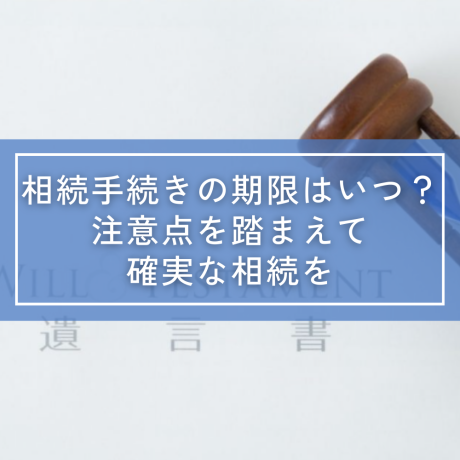
2025.09.19
相続手続きの期限はいつ?注意点を踏まえて確実な相続を
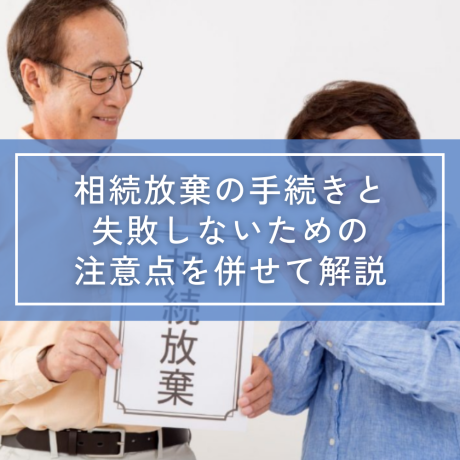
2025.09.17
相続放棄の手続きと失敗しないための注意点を併せて解説
ステップ1 -番外編:これがあれば安心!相続手続きの必要書類を知りましょう
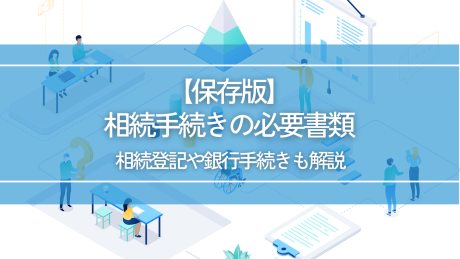
2025.05.14
【保存版】相続手続きの必要書類|相続登記や銀行手続きも解説
ステップ2 -事例:遺言書はあるけど…こんなケースはこう判断します
ステップ3:相続する?しない?を決めましょう 〜「承認」と「放棄」 の違いは?〜
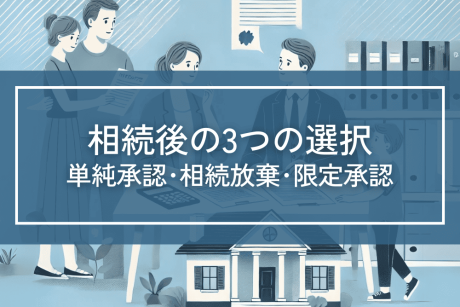
2025.05.14
相続が発生したら単純承認か相続放棄か限定承認を選択します
相続人は被相続人が死亡した場合、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。(他人に移転しない権利・義務を除く) こうした相続をするかどうか選択をすることができます。相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の三種類があります。 選択肢 説明 単純承認:相続する 被相続人の財産・債務を全て受け継ぐ 相続放棄:相続しない 全ての財産・債務を受け継がない 限定承認:条件付きで相続する 受け継いだ財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を引き受ける
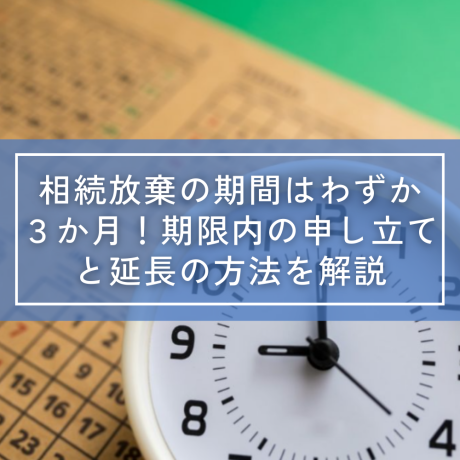
2025.12.25
相続放棄の期間はわずか3か月!期限内の申し立てと延長の方法を解説
遺産の大小に関係なく、相続を放棄する場合は、故人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。何もしなければ負債も含めて相続することになります。他の相続人に「遺産はいらない」と伝えるだけでは不十分なので注意しましょう。
ステップ3 -上級編:「相続を放棄」したい!もっと詳しく知りたい方へ
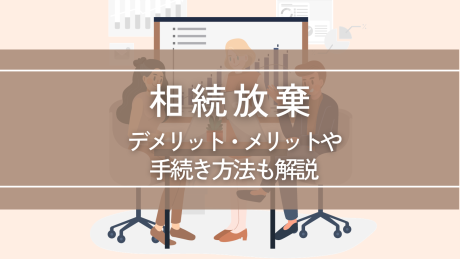
2025.05.14
相続放棄のデメリットとは?|メリットや手続き方法も解説
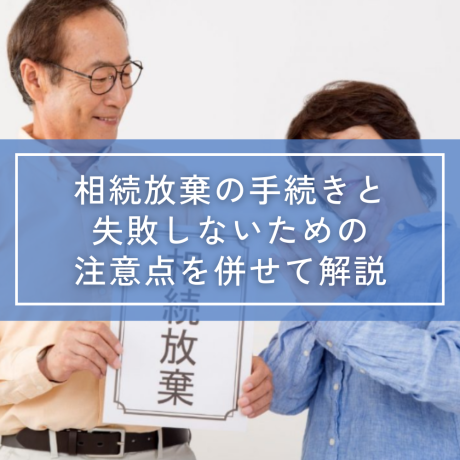
2025.09.17
相続放棄の手続きと失敗しないための注意点を併せて解説

2025.12.25
兄弟の遺産を相続放棄するには?手続きや注意点を徹底解説
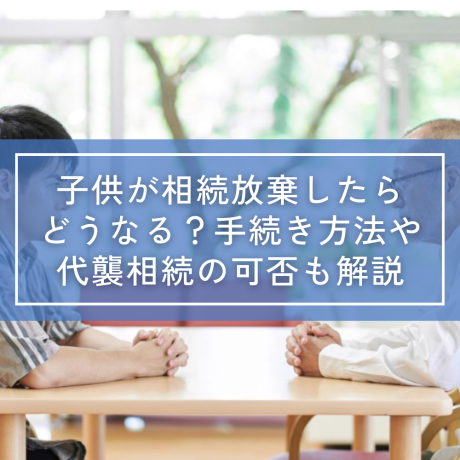
2025.12.17
子供が相続放棄したらどうなる?手続き方法や代襲相続の可否も解説
ステップ3 -上級編:「相続を承認」したい!もっと詳しく知りたい方へ
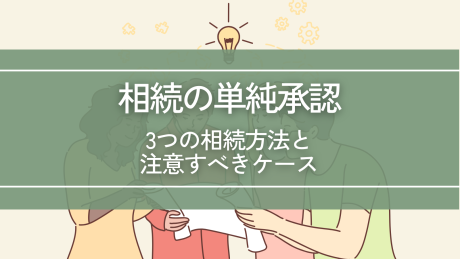
2025.12.24
相続の単純承認はどんな制度?3つの相続方法と注意すべきケース
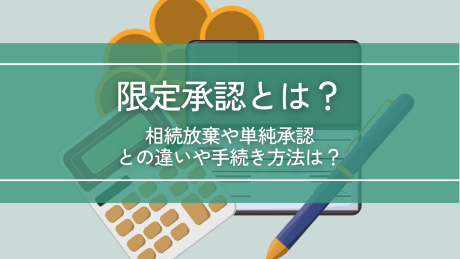
2025.12.16
限定承認を分かりやすく解説|相続放棄や単純承認との違いや手続き方法は?
ステップ4:【ここから先は相続承認者のみ!】遺言書がなければ、「遺産分割」を考えましょう
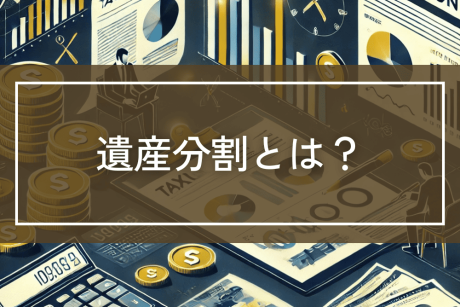
2025.05.14
相続が発生して遺言が無い場合、遺産を相続人に分配するのが遺産分割
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。
ステップ4 -上級編:お金?権利?「遺産分割」を詳しく知りましょう
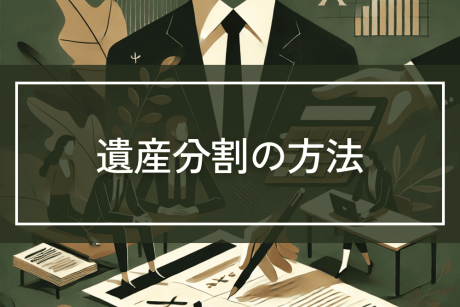
2025.05.14
相続で遺産を分割する際に主に行われる4つの方法
ステップ4 -事例:遺産分割の困った・分からない!はこう判断
ステップ5 -上級編:相続手続きをもっと詳しく知りたい方へ
ご不安がある方は、「なるべく早く」専門家に相談しましょう
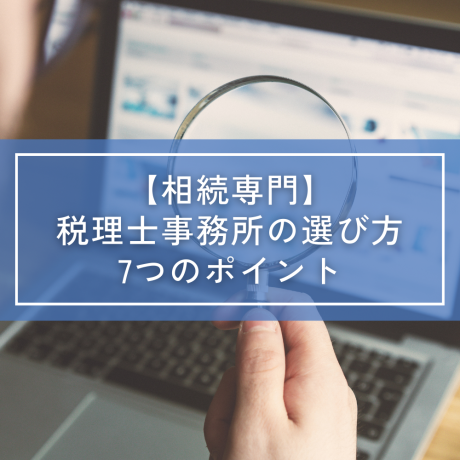
2025.05.14
相続税に強い税理士の選び方-7つのポイント
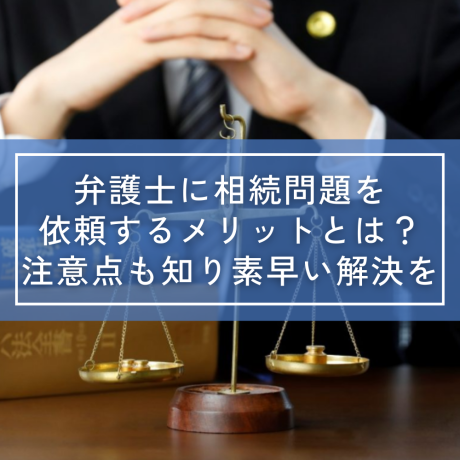
2025.12.16
弁護士に相続問題を依頼するメリットとは?注意点も知り素早い解決を
まずは無料初回面談へ
相続が発生したら焦らずまずはご相談を。必要な手続きを丁寧にサポートします。
相続税申告を考える前に:あなたは、相続税が大体いくらかかる?
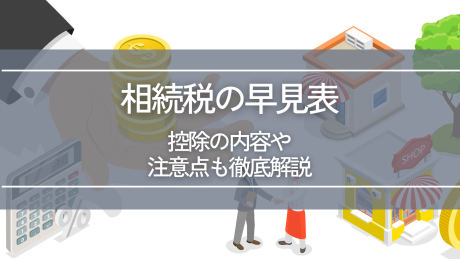
相続税の早見表で簡単チェック!控除の内容や注意点も徹底解説
早見表を確認すれば、相続税の金額がすぐに分かります。チェックする際のポイントは、「相続する財産はいくらなのか」「財産を相続するのが誰なのか」の2点です。また、亡くなった方に配偶者がいるかどうかで計算方法に違いがあるため、早見表は配偶者ありとなしの2パターンを紹介します。
ステップ1:自分で申告?専門家に依頼?判断基準は?
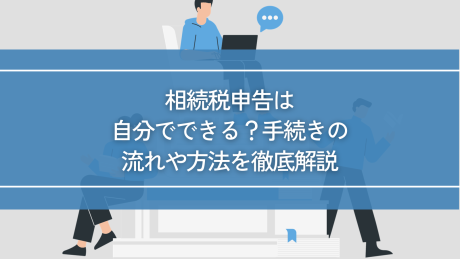
相続税申告は自分でできる?手続きの流れや方法を徹底解説
相続税の申告自体は、誰にでもできるでしょう。ただ、知識がない方が行うと財産の見落としや記載ミスなどが起こり、最終的には税務調査が入ったりペナルティが発生したりするかもしれません。 相続税は、財産の洗い出しを行う際や控除、特例などを使用する際に細かい条件が定められています。また、税金を算出する際には「限界税率」や「実効税率」、「控除額」などさまざまな数値を用いるものです。複雑で時間もかかることから、専門家である税理士に申告を任せる方は少なくありません。
ステップ2-1:使える制度を知って、税負担を減らしましょう! 〜配偶者控除編〜
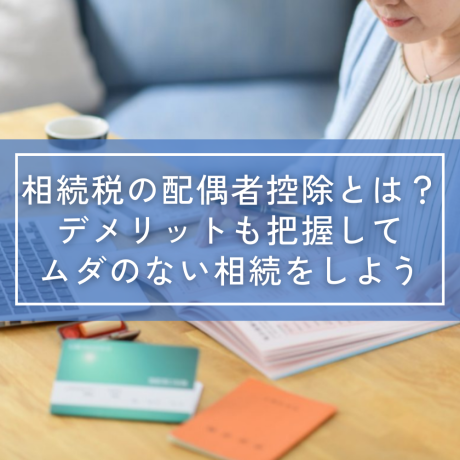
2025.05.14
相続税の配偶者控除とは?デメリットも把握してムダのない相続をしよう
ステップ2-2:使える制度を知って、税負担を減らしましょう 〜非課税になるケース編〜
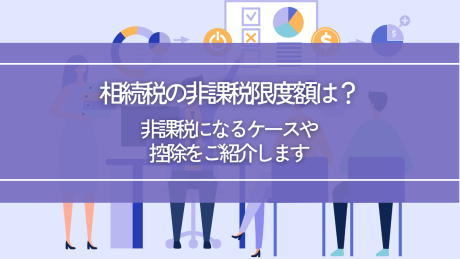
2025.12.18
相続税の非課税限度額は?非課税になるケースや控除をご紹介します
ステップ2-3:2回目の相続が近々ありそうな方はこちらもチェック!
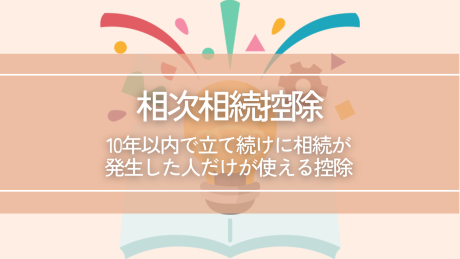
2025.09.22
【相次相続控除】10年以内で立て続けに相続が発生した人だけが使える控除
相続税申告は、安心できる相続の専門家に任せましょう
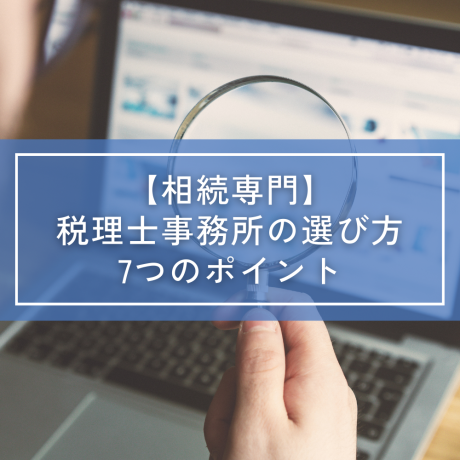
2025.05.14
相続税に強い税理士の選び方-7つのポイント
相続税申告には専門的な知識が必要です。適切なサポートを提供できる税理士事務所を選ぶことが、無駄な税金を支払うことなく相続をスムーズに進めるためのカギとなります。 そのために重要な選択基準として、以下の7つのポイントをご紹介します。
まずは無料初回面談へ
難しい相続税の申告手続きや納税のご不安も、専門家にお任せください。