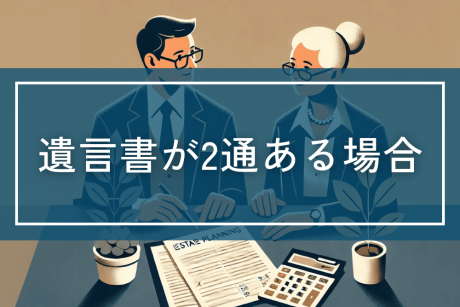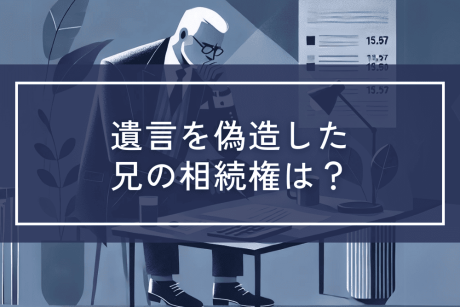投稿日:2025.10.28 最終更新日:2025.10.28
【令和7年度税制改正】扶養と年収の“壁”はどう変わる?所得税に関する主な見直し
こんにちは。中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。
本記事は、2025年4月以降に公開された国税庁の資料をもとに、令和7年度(R7)税制改正のうち所得税に関する主要論点を整理したものです。申告実務や年末調整、家計設計の再確認にお役立てください。
関連記事:令和7年度税制改正大綱~「年収・扶養の壁」はどうなる?~
はじめに:改正の全体像
令和7年度より、物価上昇局面での税負担調整と就業調整への対応の観点から、所得税の基礎控除が一部見直されます。合計所得金額が2,350万円以下の方は、令和7年度以降一律58万円以上に変更となります。
本記事では、とくに次の4点を扱います。
- 基礎控除は引き上げ。ただしR7・R8の2年間とR9以降で取扱いが異なる区分がある
- いわゆる「103万円の壁」に関する整理と、「160万円」の目安に関する説明
- 特定親族特別控除の創設(19歳以上23歳未満の家族がいる世帯への影響)
- 扶養親族等の所得要件の改正(給与収入の目安含む)
1.基礎控除額の見直し
基礎控除は、年末調整・確定申告において合計所得金額から差し引ける所得控除のひとつです。合計所得金額には給与・事業・不動産・雑所得(年金や副業等)などが含まれます。
今回の見直しでは、所得税の基礎控除が改正対象であり、住民税の基礎控除は改正対象外です。
令和7年度より、合計所得金額2,350万円以下の方は一律58万円以上となります。さらに、合計所得金額132万円(給与収入のみの場合200万3,999円)以下の方は、基礎控除額が95万円まで増額されます。
改正後の合計所得金額と基礎控除額の関係は、原文の表のとおりで、R7・R8とR9以降で132万円超~655万円以下の区分に差が生じます。
(注)
1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加えた額です。
2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した額。加算は居住者のみ適用されます。
「103万円の壁」の整理と、給与所得控除の最低額引上げ
「103万円の壁」は、給与収入に関する目安として広く知られてきました(自営業・年金など他の所得区分にはそのまま当てはまりません)。
用語整理:
- 給与収入…支給額面(年収)
- 給与所得…給与収入から給与所得控除を差し引いた額
給与所得は次の式で算出します。
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
今回、給与所得控除の最低額が見直され、R6まで:55万円(162万5,000円以下一律)から、R7から:65万円(190万円以下一律)へと引き上げられます。
また、課税所得は次式で求めます。
課税所得 = 合計所得金額 - 基礎控除 - その他の所得控除
(その他の所得控除:扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除等)
原文の「基礎控除×給与収入」の整理(ポイント1の表に給与収入欄を加味したもの)にもとづくR7以降の計算例:
- ① 年収190万円のみ
190万円 − 65万円 = 給与所得125万円 → 125万円 − 基礎控除95万円 = 課税所得30万円(課税あり) - ② 年収160万円のみ
160万円 − 65万円 = 給与所得95万円 → 95万円 − 基礎控除95万円 = 課税所得0円 - ③ 年収103万円のみ
103万円 − 65万円 = 給与所得38万円 → 38万円 − 基礎控除95万円 = 課税所得0円
このとおり、給与収入160万円で課税所得0円となるケースがあるため、「所得税が課税されない給与収入の目安」として160万円が参照される場面があります。ただし、その他の所得や各種控除の有無により結果は異なり得ます。従来の「103万円の壁」と同様に、個々の事情によって最適なラインは変動します。
(注)本節の注記は前掲「基礎控除の注記」と同一です。
特定親族特別控除の創設(19~22歳)
これまで、19歳以上23歳未満の扶養親族(いわゆる「特定扶養親族」)については、扶養控除63万円がありましたが、「103万円の壁」を超えると扶養控除が使えず、扶養する側の負担が増える課題がありました。
令和7年度改正により、特定親族特別控除が創設。居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者として給与の支払を受ける人・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方が対象です。該当する特定親族1人につき、その合計所得金額に応じて、扶養する側で最⾼63万円を控除できます。なお、親族には児童福祉法の規定による里子を含みます。
本節は所得税の扶養の説明です。社会保険上の扶養は取扱いが異なるため、個別にご確認ください。
4.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されています(給与収入の目安を併記):
- 扶養控除(扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額)…58万円以下(給与収入123万円以下)
- ひとり親控除(ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計)…58万円以下(給与収入123万円以下)
- 勤労学生控除(勤労学生の合計所得金額)…85万円以下(給与収入150万円以下)
また、給与所得控除の引上げに合わせ、家内労働者等の事業所得等の特例における必要経費の最低保障額が、65万円(改正前55万円)に引き上げられています。
要点の整理
- 給与収入123万円であれば、扶養する側は扶養控除の適用があり、扶養される本人も所得税がかからないケースが想定されます(前掲の所得要件に合致する場合)。
- 特定親族特別控除により、大学生世代の家族がいる世帯は、本人の所得に応じて控除額が段階的に変動します。毎年の状況確認が重要です。
- 本人のみで見た場合の給与収入160万円は、課税所得が0円となり得る目安として参照されます(他所得や控除の有無で異なります)。
- 所得税の扶養と社会保険の扶養は基準が異なります。就業条件の設計時には両面の確認が必要です。
実務への影響と対応ポイント
- R7年11月までの給与・公的年金等の源泉徴収事務は変更なし
- R7年分の給与の源泉徴収事務は、R7年12月の年末調整で源泉徴収税額と精算
- 従来「103万円の壁」を目安にしていた勤務条件の見直しに関する社内協議
- 年末調整・確定申告での控除額再確認と、業務システムの更新
- 源泉徴収票の記載方法の変更への社内周知
- 高所得層の資産管理・節税設計の再点検
- 住宅ローン控除・ふるさと納税・iDeCo等との併用バランスの再確認
不動産所得・事業所得・配当所得など複数の収入源がある方、また法人役員の方は、区分ごとの影響チェックと早めのシミュレーションをおすすめします。
まとめ
令和7年度改正では、基礎控除・給与所得控除・扶養関係の整理など、家計・人事実務の双方に影響するポイントが含まれます。私たちアイユーコンサルティンググループは、最新の制度に対応した申告支援と実務サポートをご用意しています。
- 個人のお客様:年末調整、確定申告、各種控除の最適化まで一括対応
- 法人・実務家の皆様:社員向けセミナー、社内説明資料の整備支援
- ご希望に応じて、対面/オンライン相談、シミュレーション(初回無料)
税務に関するご相談は、アイユーコンサルティンググループへお気軽にお寄せください。
≪出典≫
※本記事は2025年時点の国税庁資料に基づいて作成しています。制度は変更となる場合があります。