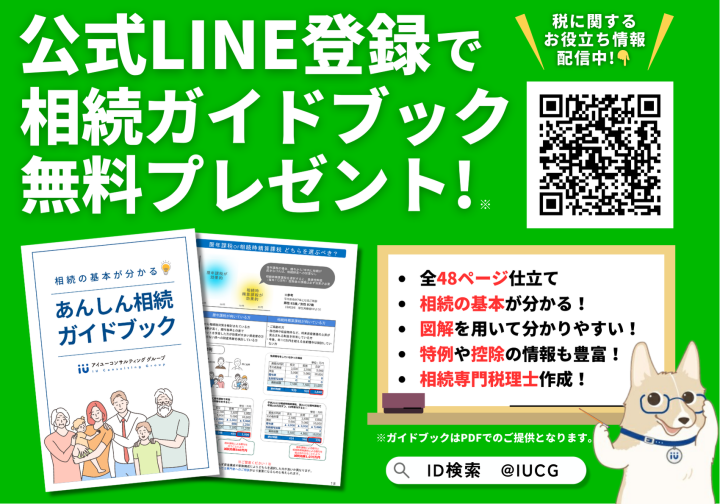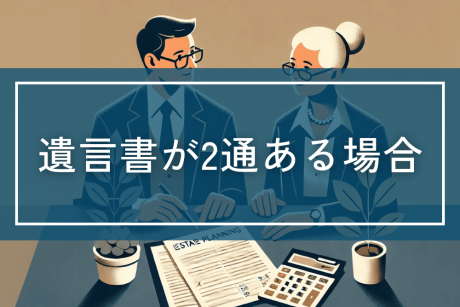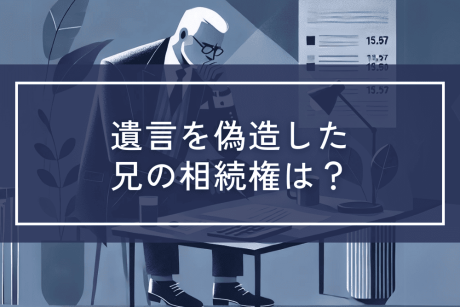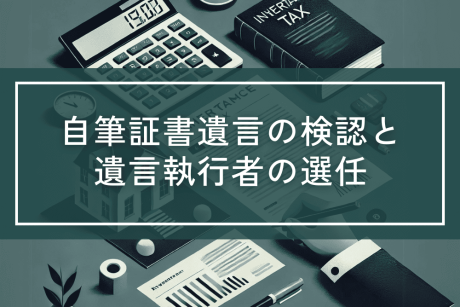投稿日:2025.10.20 最終更新日:2025.11.26
デジタル遺言はいつから?制度改正で変わる相続のかたち
こんにちは。
税理士法人を母体に中小企業・資産家向けにサービスを展開するアイユーコンサルティンググループです。
ここ最近、「デジタル遺言」という言葉を耳にする機会が増えています。これまで紙で作成するのが当たり前だった遺言書が、いよいよテクノロジーによって新しい時代を迎えようとしています。
「手続きが難しそう」「どこから始めたらいいかわからない」と感じ、遺言や相続の準備を後回しにしている方も少なくありません。しかし、2025年10月からスタートする「公正証書遺言のデジタル化」によって、相続のあり方が大きく変わります。
この記事では、制度改正のポイントや、相続実務への影響を分かりやすく解説します。
1. 遺言書の種類と現行制度の課題
現在、法的に認められている遺言書には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言:本人がすべて手書きで作成
- 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で手続きを行う
それぞれに特徴がありますが、作成や保管に手間がかかる、証人が必要、費用がかかるなどのデメリットが課題でした。こうした問題を解消するために進められているのが、遺言書の「デジタル化」です。
2. 公正証書遺言のデジタル化は2025年10月1日スタート
現在最も多く利用されている公正証書遺言は、その確実性が高い反面、公証役場での面談や署名など時間と手間がかかる手続きが課題でした。これが、2025年10月からの制度変更により大きく改善されます。
主な変更点
- オンラインで手続き可能に
公証人や証人とのやり取りをオンライン会議システム上で行うことができ、自宅や病院、施設などからも遺言書作成が可能になります。 - 電子署名で完結
署名・押印に代わり電子署名が認められ、遠方の家族や証人ともオンラインで完了できます。 - 電子データで保管・交付
遺言書はPDF形式で保管され、紙の紛失や災害リスクを軽減。相続人への交付も電子データで行えます。
これにより、公証役場へ出向く必要がなくなり、相続人が遠方にいる場合でもスムーズなやり取りが可能になります。高齢者や病院入院中の方にとっても、大きな利便性向上といえるでしょう。
3. 自筆証書遺言のデジタル化はどうなる?
一方、自筆証書遺言のデジタル化は現在も政府で検討中です。全文を手書きしなければならないという法的要件があり、これがデジタル化の大きな壁となっています。
今後の方向性として検討されているポイント
- パソコンやスマートフォンでの作成を可能にする仕組み
- マイナンバーカード等を活用した本人確認制度の導入
- 法務局による安全なデジタル保管制度の整備
自筆証書遺言のデジタル化が進めば、病気や怪我で字を書くことが難しい方でも、自身の意思を残しやすくなります。海外事例も参考にしながら、日本でも現実的な制度設計が期待されています。
4. 手続きが簡単になっても、専門家のサポートは必要
遺言作成がデジタル化され、手続きが簡単になっても、内容の正確性を担保することはとても重要です。形式や文言に不備があれば、遺言自体が無効になるリスクもあります。
こんなトラブルに注意
- 遺留分(法定相続人が最低限受け取る権利)を侵害してしまう
- 財産の内容が曖昧で相続手続きが進まない
- 相続税対策が不十分で、家族に税負担が発生する
デジタル化によって手軽に作成できるようになる一方、正しい知識や法的チェックを欠いたままでは、かえってトラブルの火種を生むことにもなりかねません。専門家と一緒に内容を検討することが、安心につながります。
5. 相続・生前対策のご相談はアイユーコンサルティンググループへ
アイユーコンサルティンググループは、相続・事業承継・生前対策を専門に、国内外15拠点で幅広いサポートを行っています。
税理士をはじめ、各士業や外部専門家などと連携し、相続税申告から遺言書作成、生前贈与、事業承継までトータルに対応いたします。
「自分の遺言をどう残せばいいか」「相続対策を始めたいが何からすればいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。