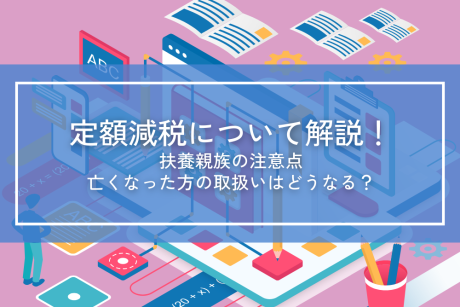WRITTEN BY 青木 恵 税理士
投稿日:2021.08.02 最終更新日:2025.12.24

相続税改正のポイント|相続法から令和7年の最新改正まで網羅解説
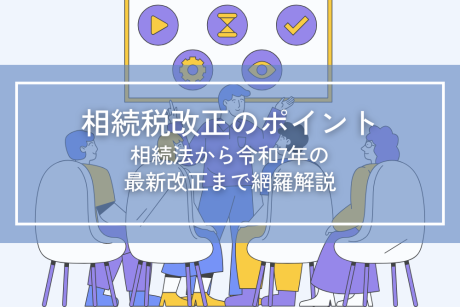
このコラムを書いた人

青木 恵 税理士
税理士法人アイユーコンサルティング 山口兼大阪事務所長
大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。
そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。
一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。
2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。
入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。
顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。
最近の相続税改正の流れとは?

経済や社会情勢の変化に合わせ、相続税に限らず税金に関する法律は毎年改正されています。広範囲にわたる改正をまとめているのが「税制改正大綱」です。税制改正大綱は毎年年末に公表されます。改正箇所を調べるには、税制改正大綱の資産課税の項目を確認するとよいでしょう。
大幅な改正があった平成25年度以降、相続税や贈与税は以下の表のように改正を重ねています。税金に関するものではありませんが、平成30年7月の相続法(民法)改正も注目すべきポイントといえるでしょう。
| 年度 | 主な改正点 |
|---|---|
| 平成25年度 | 相続税の基礎控除額や税率など多岐にわたる見直し |
| 平成26年度 | 復興支援のための税制上の措置 |
| 平成27年度 | 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設など |
| 平成28年度 | 農地保有に係る課税の強化・軽減 |
| 平成29年度 | 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し |
| 平成30年度 | 事業承継税制の拡充 |
| 平成30年7月 | ※相続法(民法)改正 |
| 令和元年度 | 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し |
| 令和2年度 | 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 |
| 令和3年度 | 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し |
| 令和4年度 | 相続登記の義務化 |
| 令和5年度 | 贈与加算期間の延長と相続時精算課税制度の改正 |
平成25年度税制改正の6つのポイント

平成25年度(2013年度)税制改正によって、基礎控除が大幅に減額しました。相続税・贈与税の税率構造の変更も重要なポイントです。ここでは、基礎控除や税率の他、小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除、相続時精算課税制度の改正に焦点を当てて、それぞれ詳しく解説します。
基礎控除が引き下げ
相続税の基礎控除が、改正前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。相続財産の金額が基礎控除以内であれば相続税の申告は必要ありません。
基礎控除額の引き下げにより、相続税の課税対象となる被相続人の数は約2倍に増加しました。例えば、東京国税局の申告事績を見ると、18万6,000人から32万2,000人に推移しています。改正前は相続税の申告が必要なかった人も、改正により課税対象となる可能性があり注意が必要です。
(参考: 『令和元年分相続税の申告事績の概要|東京国税局』)
相続税の税率構造が変更
相続税の税率改正における主な変更点は、税率構造が6段階から8段階に変更された点、最高税率が50%から55%に引き上げられた点の2点です。改正によって、各法定相続人の取得金額が2億円を上回る場合の税率が変更になりました。
| 各法定相続人の 取得金額 |
改正前の 税率 |
改正前の 控除額 |
改正後の 税率 |
改正後の 控除額 |
|---|---|---|---|---|
| ~1,000万円以下 | 10% | – | 10% | – |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
未成年者控除・障害者控除の控除額が引き上げ
未成年者控除は、相続人が未成年である場合に18歳までの年数に応じた額を相続税額から差し引ける制度です。同様に、障害者控除では相続人が障害者である場合に85歳までの年数に応じた額を控除できます。いずれも改正によって控除額が引き上げられました。
・未成年者控除の控除額の改正点 ※改正当時は20歳に達するまでの年齢
| 改正前 | 18歳に達するまでの年齢×6万円 |
|---|---|
| 改正後 | 18歳に達するまでの年齢×10万円 |
・障害者控除の控除額の改正点
【一般障害者】
| 改正前 | 改正前85歳に達するまでの年齢×6万円 |
|---|---|
| 改正後 | 85歳に達するまでの年齢×10万円 |
【特別障害者】
| 改正前 | 85歳に達するまでの年齢×12万円 |
|---|---|
| 改正後 | 85歳に達するまでの年齢×20万円 |
小規模宅地等の特例を適用できる土地面積が拡大
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業を行っていた土地がある場合、一定の面積まで相続税上の評価額を最大80%減額できる制度です。平成25年度税制改正によって、限度面積の上限が引き上げられています。
・居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積
| 改正前 | 限度面積240平方メートル |
|---|---|
| 改正後 | 限度面積330平方メートル |
・居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
| 改正前 | 合計400平方メートルまで適用可能 |
|---|---|
| 改正後 | 合計730平方メートルまで適用可能 |
相続時精算課税制度の適用要件が変更
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たす場合に最大2,500万円までであれば贈与税を納めずに父母または祖父母から贈与を受けられる課税方式です。
相続時精算課税制度を選択して贈与された財産は、贈与者である父母または祖父母が亡くなったときに相続財産と合わせて相続税の課税対象となります。相続時精算課税制度の適用要件は以下のように変更されました。
・贈与者 ※改正当時は20歳以上の者
| 改正前 | 贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 |
|---|---|
| 改正後 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上の者 |
・受贈者
| 改正前 | 贈与時において贈与者の推定相続人で18歳以上の者 |
|---|---|
| 改正後 | 贈与時において贈与者の推定相続人および孫で18歳以上の者 |
贈与税(暦年課税)の税率構造が変更
相続税と同じく、税率構造が6段階から8段階に変更され、最高税率が50%から55%に引き上げられました。また、税率が一般贈与財産用の「一般税率」と特例贈与財産用の「特例税率」に分けられた点もポイントです。
特例税率は、祖父母や父母といった直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に適用されます。一方、一般税率は特例税率が適用されない贈与に関する税率です。
| 基礎控除後の課税価格 | 改正前 | 改正後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 控除額 | 一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 | |
| ~200万円以下 | 10% | – | 10% | – | 10% | – |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | ||
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 | ||
| 4,500万円超~ | 55% | 640万円 | ||||
平成30年7月に成立した相続法改正の内容とは?

「人が亡くなったとき、財産をどのように承継するか」ということに関して民法で定めている基本ルールを「相続法」などと呼びます。高齢化社会による社会構造の変化を背景として、平成30年(2018年)7月に相続法の改正が成立しました。ここでは、相続法改正の内容について解説します。
配偶者が自宅に住み続けられるようになった
例えば、被相続人の相続財産が自宅(土地・建物)3,000万円と預貯金3,000万円のケースで、妻と子が法定相続分の1/2ずつ財産を受け取るとします。妻が3,000万円の自宅、子が預貯金3,000万円を相続すると、妻には生活費が残りません。一方、預貯金を得ると、住む場所に困るでしょう。
新たに創設された「配偶者居住権」を活用することで、配偶者は自宅に住み続けられるようになりました。子は「負担付きの所有権」を取得するため、その分の預貯金を妻が得られます。
配偶者居住権は売ったり貸したりできない分、財産評価額を低く抑えられるのが特徴です。配偶者は自宅に住み続けながら預貯金といった財産が取得できるため、生活の安定につながるでしょう。
結婚して20年以上の夫婦は自宅の贈与・遺贈が遺産分割の対象外となった
生前に自宅を配偶者に贈与した場合、計算上、相続財産として扱われないこととされました。なお、婚姻関係が20年以上である点に注意が必要です。
改正前は配偶者の生活の安定のために自宅を生前贈与しても、贈与した自宅は相続財産として取り扱われ、相続時に受け取れる財産が減るというデメリットがありました。改正によって自宅は相続財産に含まれないこととなり、配偶者はより多くの財産を受け取れるようになります。
遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払い戻しができるようになった
遺産分割の対象となる預貯金に関して、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で払い戻せるようになりました。改正前は生活費や葬式費用の支払いに困るといった問題がありましたが、現在は遺産分割前でも一定額については金融機関で払い戻しが可能です。預貯金の払い戻し方法には、次の2つがあります。
・家庭裁判所に申し立てる
他の共同相続人の利益を害さない範囲で、家庭裁判所の判断による仮払いが可能です。
・金融機関の窓口で手続きをする
法定相続分の3分の1を上限に、同一の金融機関につき150万円までは他の共同相続人の合意を得ずに払い戻せます。
遺言書の一部をパソコンで作成できるようになった
今まで全て手書きで作成する必要があった自筆証書遺言のうち、財産目録はパソコンで作成できるようになりました。通帳のコピーも添付できるようになり、手書きの負担が軽減されます。
なお、パソコンやコピーで作成した財産目録には、本人の意思で作成したことを証明するために全ページに署名押印する必要がある点に注意しましょう。
法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設された
法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の保管を申請できるようになり、「遺言書が見つからない」「紛失してしまった」といったトラブルを防げるようになりました。遺言書を作成した本人が手続きする必要があるため、本人の意思で作成したことを確認できる点もメリットといえるでしょう。
法定相続人は被相続人が亡くなった後に、法務局(遺言書保管所)に遺言書が保管されているかどうかの調査や遺言書の閲覧ができます。
無償で被相続人の介護を行った場合に長男の妻などが金銭を請求できるようになった
法定相続人以外の親族が無償で被相続人の介護などを行った場合に、法定相続人に対して金銭を請求できるようになりました。「長男の妻が義父である被相続人の介護に尽くしても相続財産は受け取れない」といった不公平感を解消するための改正です。
令和3年度税制改正のポイント

令和3年度(2021年度)における相続税・贈与税の税制改正は、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の他、直系尊属から住宅取得等資金の贈与に関する制度や特例が主なポイントです。ここでは、それぞれの改正ポイントについて解説します。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度 ※令和5年度に改正があります。
適用期限が令和5年3月31日まで2年間延長され、相続税の課税対象が「贈与者の死亡前3年以内の贈与」から「贈与から経過した年数にかかわらず贈与者死亡時の残高」に変更されました。ただし、受贈者が次の3つの要件に該当する場合はその限りではありません。
- 23歳未満
- 学校に在学中である
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
受贈者が贈与者の孫やひ孫のような子以外の直系卑属である場合、贈与者死亡時の残高に対する相続税額に2割加算が適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度 ※令和5年度・7年度に改正があります。
教育資金の一括贈与と同じく、適用期限が令和5年3月31日まで2年間延長され、贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)である場合も同様に2割加算の対象となりました。また、受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
※令和5年度改正により、適用期間が令和7年3月31日まで2年間延長されました。契約終了時の贈与税は一般税率で計算することとなりました。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 ※令和6年度に改正があります。
原則、相続時精算課税制度を選択するには、贈与者である父母または祖父母が60歳以上である必要があります。ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たすことで贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税制度の選択が可能です。この制度を「相続時精算課税の特例」といいます。
さらに、床面積要件の下限が50平方メートル以上から40平方メートル以上に引き下げられました。
令和4年度税制改正のポイント
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置の延長
適用期限が令和5年3月31日まで2年間延長され、既存住宅家屋の要件について築年数要件の廃止及び新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。
さらに受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられました。
非課税限度額については下記のように改正となりました。
良質な住宅家屋:1,000万円
上記以外の家屋: 500万円
相続登記の義務化
相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内登記を行うことが義務化されました。2024年(令和6年)4月1日より適用開始の予定です。
令和5年度税制改正のポイント
贈与加算期間の延長
相続または遺贈により財産を取得する方が被相続人から生前に贈与を受けていた場合、贈与加算期間が7年に見直されました。
2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産について適用される予定です。
相続時精算課税制度の改正
贈与加算期間の延長に伴い、相続時精算課税制度では毎年110万円の基礎控除ができることとなりました。また、相続時精算課税制度で贈与を受けた土地または建物が災害によって被害を受けた場合は、被害に相当する額を控除して相続税の計算をすることができるようになりました。
110万円の控除については、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される予定です。
災害により被害を受けた場合の計算については、2024年(令和6年)1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用される予定です。
教育資金の一括贈与の延長
適用期限が2026年(令和8年)3月31日まで3年間延長され、贈与日から教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合で、その贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満等であっても、管理残額は受贈者が相続により取得したものとみなされるようになりました。
また、受贈者の年齢が30歳に達したこと等により、契約終了時の管理残額に贈与税が課される場合、一般税率が適用されることとなります。
2023年(令和5年)4月1日以後に取得する教育資金に係る贈与税・相続税について適用されます。
マンションに係る評価の見直し
2024年1月1日以後の相続、遺贈、贈与で取得したマンションについて評価方法が変更されます。
マンションの市場での売買価格と、通達に基づく相続税評価額との乖離率は全国平均で2.3倍程度とされており、評価額と市場価格との乖離を是正するために本通達が制定されました。
詳細な評価方法などは、下記の弊社ブログ記事をご覧ください。
参考:マンション評価を再確認!令和6年1月1日からの評価方法について
令和6年度税制改正のポイント
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置等の延長
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限が2026年(令和8年)12月31日まで3年延長(改正前2023年(令和5年)12月31日まで)されました。
また、省エネ等住宅の適用対象となる新築(未使用)住宅用家屋について、省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上に一部要件が変更されました。
事業承継税制の提出期限延長
非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けるための『特例承継計画』の提出期限が、2024年(令和6年)3月31日から2年延長し、2026年(令和8年)3月31日までとなります。
同様に、個人版事業承継税制の『個人事業承継計画』についても提出期限が2年延長されます。
【最新】令和7年度税制改正のポイント
直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税につき、非課税措置の適用期限が2027年(令和9年)3月31日まで2年間延長されます。制度内容の改正はありません。
事業承継税制の要件緩和
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例(法人版事業承継税制)を受けるための役員就任要件について、受贈者が「贈与の日まで引き続き3年以上役員であること」から、「贈与の直前においても役員であること」へ緩和されます。同様に、個人版事業承継税制(2028年(令和10年)12月31日まで)の事業従事要件についても、3年以上から直前へ緩和されます。
損をしない相続をしたいならアイユーコンサルティング!
相続税は定期的に改正されており、正しく制度を理解し申告するには専門家に力を借りるのが確実でしょう。改正点を把握せずに申告すると、本来受けられる恩恵を享受できず、思わぬ損をしてしまうかもしれません。相続で損をしたくないのであれば、豊富な専門知識を持つアイユーコンサルティングにお任せください。
・最大限の節税、相続対策のご提案
「お客様の財産を無駄なく承継し、永続させるお手伝い」を念頭に、資産税のプロとして最大限の節税・相続対策をご提案します。
・累計4,350件以上の豊富な実績
アイユーコンサルティングの累計実績は相続・承継案件だけで4,350件以上です。一般的な税理士事務所の約30倍という数値を誇ります。
・戸籍取得・名義変更手続きの代行サービス
まとめ

大きな改正から小さな改正まで、相続税の制度は時代に合わせて絶えず変化しています。最新の正しい知識に基づいて相続税の申告をするには、税理士のような専門家を頼るのもひとつの方法です。
「自分で正しく相続税申告をするのは難しそう」「忙しくて相続税申告の手続きに時間が割けない」という方は、ぜひ相続のプロ集団であるアイユーコンサルティングにお任せください。アイユーコンサルティングではWEB相談も受け付けており、ご自宅から気軽にご相談いただけます。
このコラムを書いた人

青木 恵 税理士
税理士法人アイユーコンサルティング 山口兼大阪事務所長
大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。
そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。
一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。
2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。
入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。
顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。