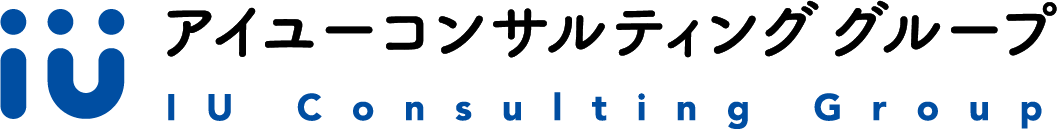争いも無理もなく、相続する側もされる側も納得のいく円満な相続のために、アイユーコンサルティングでは3つの生前対策「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」を行うことをお勧めしております。
生前対策について
生前に行う節税対策
「節税対策」は、生前に財産を贈与する「生前贈与」を利用して相続税の納税額そのものを減らす方法です。
節税対策で初めに重要なのは現状把握をすることです。
相続税の対象となる財産がいくらあるか把握することで、具体的な節税対策に取り掛かることが出来ます。
試算致しますので、お気軽にご連絡ください。
→生命保険を活用した納税資金の確保(⑩生前贈与として生命保険を活用した納税資金の確保へリンク)
→納税資金確保活用のご相談はこちら
生前に行う納税資金の確保
相続税を納めるための「納税資金の確保」も、節税対策と共に行う必要があります。
相続税の納税は原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に「金銭一時納付」で納税しなければなりません。相続財産の大半が現金化が困難な財産(不動産など)で、10ヶ月以内に納税資金を用意できなかった場合、相続税を支払うために、多額の借入を迫られることになってしまいます。
「納税資金」は、生命保険金を活用して確保することができます。納税資金が用意できないというの事態を避けるためにも、お早めにご相談下さい。
→生命保険を活用した納税資金の確保(⑩生前贈与として生命保険を活用した納税資金の確保へリンク)
→納税資金確保活用のご相談はこちら
生前に行う争族対策
相続人同士で、遺産争いをすることを「争族」といいます。遺産争いをしていると、相続人が不幸になるだけでなく、相続税法の最大の特典である小規模宅地の評価減と配偶者の税額軽減も使えなくなり、相続税も高くなってしまいます。
争族対策に最も有効なのは、「遺言書の作成」です。遺言は相続において最も強い力を持っていますので、厳格な書式が求められます。また、専門的な知識や必要書類がありますが、アイユーコンサルティングでは、わかりやすく遺言書の作成のアドバイスや、原案の作成を行っております。お気軽にご連絡ください。
◆争族対策のための遺言書作成
→効果のある遺言書を作るポイント
→遺言書の作成のご相談はこちら